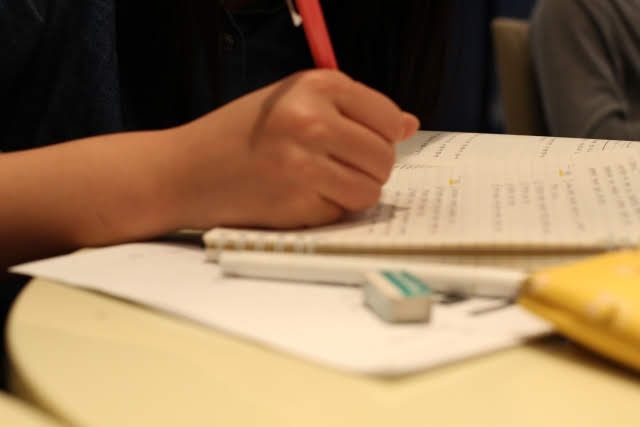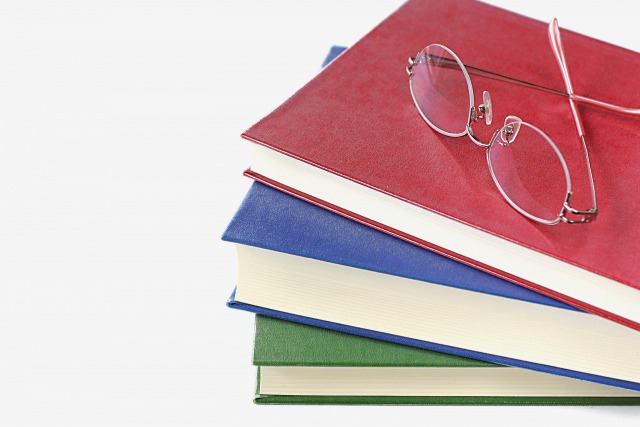少し前から電動キックボードについて気になっており、色々と調べています。
その結果わかったことですが、電動キックボードも正しく使わなければ交通事故を起こす可能性があり、当然に罰則があります。
今回は電動キックボードに適用される交通ルールと、罰則について書いていきたいと思います。

電動キックボードも青キップ対象の可能性あり
電動キックボードは、特定小型原動機付自転車とも呼ばれており、道路上を運転する際には当然に交通ルールが適用されます。
電動キックボードのルールは、自動車のルールとも似ている気がします。というのは、交通反則通告制度(青キップ)や放置違反金制度の対象です。
違反をした場合は、交通反則通告制度などで処分される可能性がありますが、一定期間内に反則金を納めれば刑事罰は科せられません。
もちろん違反はしない方が絶対にいいと思います。乗る前にしっかりルールの確認が必要ですね。
16歳未満の運転は禁止
電動キックボードを運転するのに、運転免許は必要ありません。運転免許証を持っていない場合、バイクや車の運転は難しいのですが、電動キックボードなら乗れそうですね。
年齢制限があり、16歳未満の人が運転することは禁止されていますし、16歳未満の人に対して電動キックボードを貸すこともできません。
子どもがいる場合など、子どもが電動キックボードに乗って運転したいとせがまれる場合があると思いますが、どんなにせがまれても子どもに運転させることはできないので、注意が必要です。
もし16歳未満の人が電動キックボードを運転した場合や、16歳未満の人に貸した場合には罰則があり、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
飲酒運転は絶対にダメ!
自動車の運転と同様に、お酒を飲んだときは絶対に運転してはいけません。
さらに飲酒運転をするおそれがある人に電動キックボードを貸すことや、電動キックボードを使う予定の人に対してお酒類を提供・飲酒を勧めることも当然に禁止されます。
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金という厳しい罰則があります。飲酒運転については、飲酒運転をした本人だけでなく、お酒を提供した人も処罰されるので、要注意です。
二人乗り運転やスマホ運転もダメ
電動キックボードは、二人乗りはできません。安全面を考えると、これは妥当なルールだと思います。
自動車や自転車の運転と同様に、運転中にスマートフォンで通話しながらの運転、スマートフォンの画面を見たりしながら運転することも禁止です。
電動キックボードは、自動車や自転車よりコンパクトで、手軽に利用できそうなイメージがあります。しかし使い方を間違うなら、重大な交通事故を起こす可能性もあるので、ルールはしっかり守りましょう。
政府の広報には、イラスト付きで詳しい情報が載せられています。以下のリンクもぜひご覧ください。